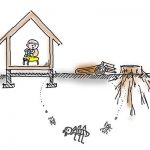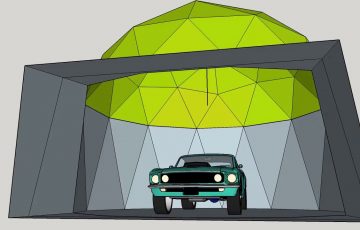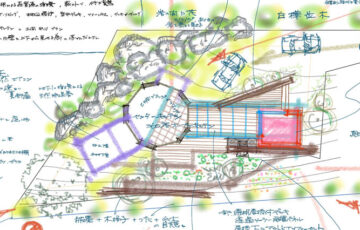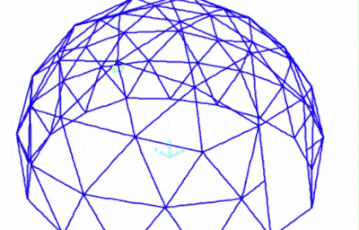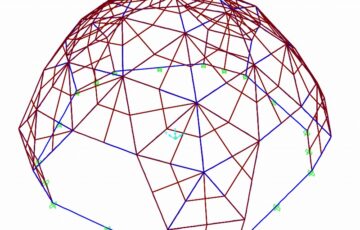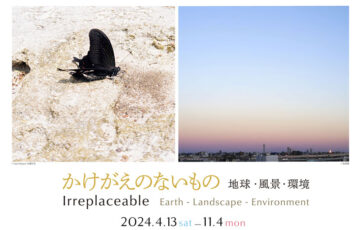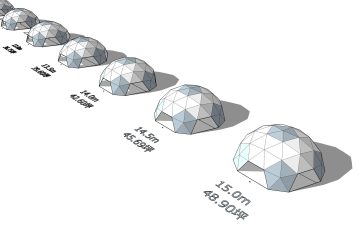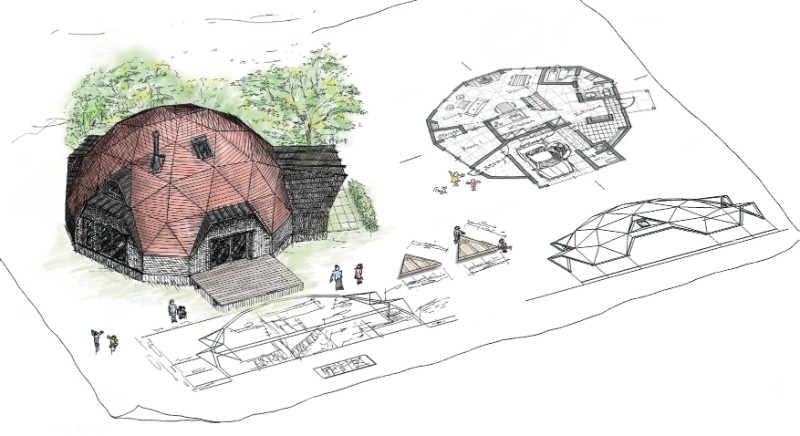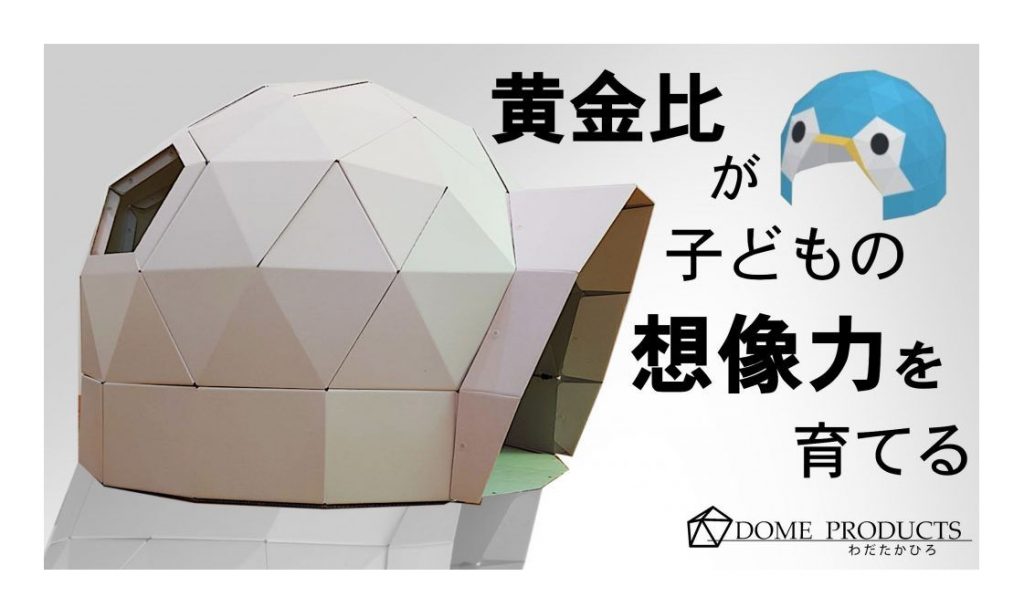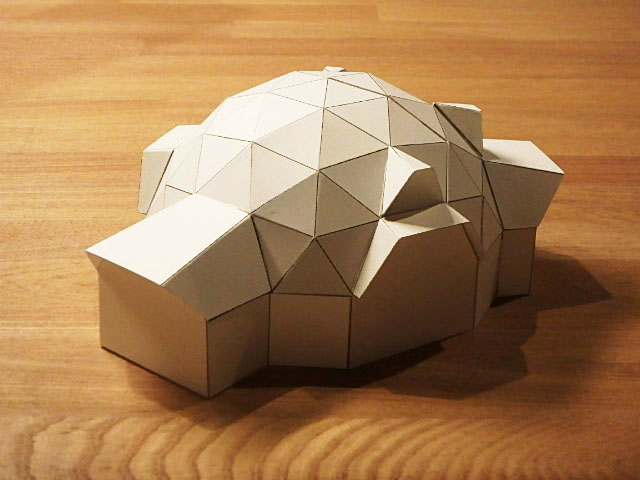我が家の薪ストーブ話での、いろいろな実験や試行錯誤の根拠となる数値がこちら。
- 薪は90~95℃以上になると、表面から水分が蒸発する。
- 薪が260℃以上になると、リグニンとセルローズが熱分解され、ガスが放出される。
- ガスを600℃に熱すると発火する。
- 薪は燃えて700℃になると、真っ赤な炭(オキ)になる。
これをまとめると、
- 700℃のオキをつくり
- その上に新しい薪を載せ
- 260℃以上に熱し
- 可燃性ガスを発生させ
- 炉内上部を600℃に熱し
- ガスを発火させる。
これが1次燃焼+2次燃焼の再現方法です。
薪を燃やし、煙も燃やす。
高効率ストーブの科学です。
そして、そんな良い燃やし方をするために一番大切なのが「薪」です。
こちらが切って2週間のコナラを割った薪。

含水率 42.5%
びしょびしょですね。
次に、20cmくらいの細いコナラを切って1年転がしておいた薪を、
内部を測定するために割ってみたところです。

含水率 18.0%
皮付きのままだと乾かないと思っていましたが、案外乾いていました。
最後が、割った状態で1年半、屋根のあるところで乾燥させたケヤキです。

含水率 11.5%
このケヤキは機械でも割れないほど堅かったのですが、それでも1年ちょっとで乾いていました。
乾燥した薪だけを使い、高温で2次燃焼をさせる使い方に徹すれば、煙突掃除が必要なくなるほど、完全に燃えてくれます。
安全で暖かく、効率の良い燃焼をさせるには、ストーブだけでなく薪の質も大切なのです。